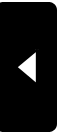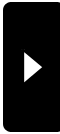› 健康スポーツの何でも屋! › ■運 動
› 健康スポーツの何でも屋! › ■運 動2016年07月18日
走るを科学する…走りのためのフィジカルトレーニング講座
スポーツの家庭教師の中で非常に人気あるジョギングクラブ…そろそろ気温が高くなりますので、しばらく休講となります。スイムクラブ以上に人気ある講座で、最近は、キャンセル待ち(1講座20名まで)状態です。
スポーツ指導は、科学的検証されたものが少ないため、カラダで教える的な部分が多くなっています。当講座は、分かり易く構成してあり、夏休みの自由研究に取り入れているお子さんもいらっしゃいます。今回は、走る…を科学してみましょう。

スポーツ中の肩の動きって考えたことってありますでしょうか?
スポーツは、肩甲骨と骨盤の動きを連動させるのが大事!とか唱える方もいらっしゃいますが、科学的根拠を説明して頂いた記憶がありません。そこで、肩の動きについて、一緒に考えてみましょう。肩の動きは、肩関節と肩甲骨の2つの関節の動きが伴います。
肩関節の動きは…
・腕を前後に動かす屈曲・伸展
・手のひらを回す外旋・内旋
・腕を横に開く外転・内転
肩甲骨の動きは…
・外側に開き内側寄せる内外転
・60度の上下に回りながら動く上方・下方回旋
・肩関節の動きを補助する下制
肩関節と肩甲骨の動き…
・肩甲骨の内外転は、肩関節の屈曲・伸展動作に作用する
・肩甲骨の上方・下方回旋は、肩関節の外旋・内旋動作に作用する
・肩甲骨の下制は、肩関節の外転・内転動作に作用する
例えば、ランニング中には、肩の屈曲・伸展、肩の外旋・内旋、肩甲骨の内転・外転動作と考えます…って想像しても頭の中がこんがらがりますよね。つまり、腕を回すだけでイイのです。
しかし、ただ腕を回すだけでは、ランニング中の肩の動きや機能の改善や向上につながりません。機能性を高めつつ、よく言われると肩甲骨と骨盤の動きを連動させる股関節・体幹の連動性が加わる体操を行います。
肩甲骨と骨盤の動きを連動させる体操
・股関節伸ばし
https://youtu.be/aLwfH1PzwXA
・肩入れ
https://youtu.be/4t4WCPSc0H4
・ひじ内まわし
https://youtu.be/zylm3UySaiw
更に強度の高い走りを求めたい方は、そのストレスに応じたフィジカルトレーニングが必要になりますけれど、体操プルグラムに歩き・走りのドリル練習を加えることで、あっと言う間に、同じキョリ・同じスピードであっても、出力が下げられ、燃費の良い走りを再現できるようになります。
かけっこが遅くて悩んでいるお子さん、運動会でお子さんに良いところを見せたいお父さん、チームの中で走りが遅くて良い練習が出来ないで悩んでいるアスリートさん、前回よりもタイムアップをはかりたいマラソンランナーさん…走りのためのフィジカルトレーニング講座は、誰でも参加出来ますよ。
あなたにとって良い走りとは、何なのか?一緒に考え、学びながら、楽しく練習しましょうね。
スポーツ指導は、科学的検証されたものが少ないため、カラダで教える的な部分が多くなっています。当講座は、分かり易く構成してあり、夏休みの自由研究に取り入れているお子さんもいらっしゃいます。今回は、走る…を科学してみましょう。

スポーツ中の肩の動きって考えたことってありますでしょうか?
スポーツは、肩甲骨と骨盤の動きを連動させるのが大事!とか唱える方もいらっしゃいますが、科学的根拠を説明して頂いた記憶がありません。そこで、肩の動きについて、一緒に考えてみましょう。肩の動きは、肩関節と肩甲骨の2つの関節の動きが伴います。
肩関節の動きは…
・腕を前後に動かす屈曲・伸展
・手のひらを回す外旋・内旋
・腕を横に開く外転・内転
肩甲骨の動きは…
・外側に開き内側寄せる内外転
・60度の上下に回りながら動く上方・下方回旋
・肩関節の動きを補助する下制
肩関節と肩甲骨の動き…
・肩甲骨の内外転は、肩関節の屈曲・伸展動作に作用する
・肩甲骨の上方・下方回旋は、肩関節の外旋・内旋動作に作用する
・肩甲骨の下制は、肩関節の外転・内転動作に作用する
例えば、ランニング中には、肩の屈曲・伸展、肩の外旋・内旋、肩甲骨の内転・外転動作と考えます…って想像しても頭の中がこんがらがりますよね。つまり、腕を回すだけでイイのです。
しかし、ただ腕を回すだけでは、ランニング中の肩の動きや機能の改善や向上につながりません。機能性を高めつつ、よく言われると肩甲骨と骨盤の動きを連動させる股関節・体幹の連動性が加わる体操を行います。
肩甲骨と骨盤の動きを連動させる体操
・股関節伸ばし
https://youtu.be/aLwfH1PzwXA
・肩入れ
https://youtu.be/4t4WCPSc0H4
・ひじ内まわし
https://youtu.be/zylm3UySaiw
更に強度の高い走りを求めたい方は、そのストレスに応じたフィジカルトレーニングが必要になりますけれど、体操プルグラムに歩き・走りのドリル練習を加えることで、あっと言う間に、同じキョリ・同じスピードであっても、出力が下げられ、燃費の良い走りを再現できるようになります。
かけっこが遅くて悩んでいるお子さん、運動会でお子さんに良いところを見せたいお父さん、チームの中で走りが遅くて良い練習が出来ないで悩んでいるアスリートさん、前回よりもタイムアップをはかりたいマラソンランナーさん…走りのためのフィジカルトレーニング講座は、誰でも参加出来ますよ。
あなたにとって良い走りとは、何なのか?一緒に考え、学びながら、楽しく練習しましょうね。
2016年07月12日
誤った前屈チェックについて
歳を取るとカラダが硬くなります。
硬くなる原因は、簡単に言えば関節周辺が硬くなる…ですが、歳を取って活動量が減ると、それだけ細胞に栄養が必要なくなりますので、血液量が減り、筋細胞が減り筋肉が痩せた状態になります。そうなると筋肉の弾力性が失われたり、血管が緊張したり、神経が緊張したりで、総合的に硬くなります。これが関節が硬くなるのメカニズムです。
カラダの一部が硬くなる訳では、ありませんが、日本人は、ココが悪いという良い訳が欲しい人種なので、ある一部の関節が固まると動きがさらにぎこちなくなって、別の関節にも負担がかかり、その関節も固まることになる…と思われています。
いわば、歳を追う毎に硬くなるは、筋肉・血管・神経・皮膚等が上乗せ上乗せで柔軟性が失われ、錆びた自転車のようになっていくのです。
可動範囲が大きな関節で、他の関節に一番影響があるのは、股関節だと思われます。股関節が固ければ、膝や足首の関節も硬くなります。膝や足首の関節が硬くなると、逆にまた股関節も固くなり、肩関節も硬くなります。
この辺りは、やまおく体操をすることで、連動していることが体感出来ますね。
通常は、連動している意味(神経筋制御)を知らない方が多いので、末端から緩めていくか、体幹からゆるめていくか、と考えるようになったのでしょう。実際は、体幹の動きが良ければ、末端は、硬くなりません。
カラダが硬いかどうかチェックする方法で一番分かりやすいのが、前屈チェックです。

前屈が出来ない理由は、股関節周りの筋肉が固まってしまっていること、太股のウラの筋肉が固くなっているせいと考えるでしょう。
しかし、基本的なやまおく体操をすると柔らかくなります。
・ひじ引き https://www.youtube.com/watch?v=tEwl1GrIWnA
・上体振り子 https://www.youtube.com/watch?v=knj26VxFgWQ
・ひざ屈伸 https://www.youtube.com/watch?v=xRn6ZeNltZ8
ですので、この考えは、間違えていることになりますね。その間違えた考えのもとストレッチやマッサージが横行しているため、何らかの原因でカラダの不調に悩む方が増えたのかも知れませんね。いわゆるコレも自律神経失調の一種です。
太股のウラの筋肉は、いわゆるハムストリングスと呼ばれる大腿二頭筋です。日本人は、骨盤後傾が大半ですので、ハムストリングを使って動作をしていません。そのため、動きが固くなってしまいます。
そのため前屈チェックが苦手なヒトが存在するのでしょうね 笑。
硬くなる原因は、簡単に言えば関節周辺が硬くなる…ですが、歳を取って活動量が減ると、それだけ細胞に栄養が必要なくなりますので、血液量が減り、筋細胞が減り筋肉が痩せた状態になります。そうなると筋肉の弾力性が失われたり、血管が緊張したり、神経が緊張したりで、総合的に硬くなります。これが関節が硬くなるのメカニズムです。
カラダの一部が硬くなる訳では、ありませんが、日本人は、ココが悪いという良い訳が欲しい人種なので、ある一部の関節が固まると動きがさらにぎこちなくなって、別の関節にも負担がかかり、その関節も固まることになる…と思われています。
いわば、歳を追う毎に硬くなるは、筋肉・血管・神経・皮膚等が上乗せ上乗せで柔軟性が失われ、錆びた自転車のようになっていくのです。
可動範囲が大きな関節で、他の関節に一番影響があるのは、股関節だと思われます。股関節が固ければ、膝や足首の関節も硬くなります。膝や足首の関節が硬くなると、逆にまた股関節も固くなり、肩関節も硬くなります。
この辺りは、やまおく体操をすることで、連動していることが体感出来ますね。
通常は、連動している意味(神経筋制御)を知らない方が多いので、末端から緩めていくか、体幹からゆるめていくか、と考えるようになったのでしょう。実際は、体幹の動きが良ければ、末端は、硬くなりません。
カラダが硬いかどうかチェックする方法で一番分かりやすいのが、前屈チェックです。

前屈が出来ない理由は、股関節周りの筋肉が固まってしまっていること、太股のウラの筋肉が固くなっているせいと考えるでしょう。
しかし、基本的なやまおく体操をすると柔らかくなります。
・ひじ引き https://www.youtube.com/watch?v=tEwl1GrIWnA
・上体振り子 https://www.youtube.com/watch?v=knj26VxFgWQ
・ひざ屈伸 https://www.youtube.com/watch?v=xRn6ZeNltZ8
ですので、この考えは、間違えていることになりますね。その間違えた考えのもとストレッチやマッサージが横行しているため、何らかの原因でカラダの不調に悩む方が増えたのかも知れませんね。いわゆるコレも自律神経失調の一種です。
太股のウラの筋肉は、いわゆるハムストリングスと呼ばれる大腿二頭筋です。日本人は、骨盤後傾が大半ですので、ハムストリングを使って動作をしていません。そのため、動きが固くなってしまいます。
そのため前屈チェックが苦手なヒトが存在するのでしょうね 笑。
2016年07月03日
サンポート高松トライアスロン2016 アフターケア
山奥コーチが個人的に契約しているトライアスリートが、サンポート高松トライアスロン2016に出場していましたので、応援に行きました。
準備体操は、先日のブログにもあった神経と筋の調和を整える様式での体操3種です。みんな会場でしていたので、え?何あの集団って感じだったのでは、無いでしょうか…笑。
整理体操にも使える基本の体操です。疲れが心配な方、また、別にレースに出場しなくても、健康体操として取り入れられますので、以下の方法をお試くださいね。

1.前屈チェックをしてみましょう。
2.次に以下の体操をしてみましょう。
ひじ引き
https://www.youtube.com/watch?v=tEwl1GrIWnA
上体振り子
https://www.youtube.com/watch?v=knj26VxFgWQ
ひざ屈伸
https://www.youtube.com/watch?v=xRn6ZeNltZ8
3.前屈チェックをしてみましょう。
あらっ不思議!!ストレッチをしたわけじゃないのに、リセットされましたね。
コレは、通常の生活で失われていた神経と筋の調和を1.でチェックして、2.の体操ををすることで、神経と筋の調和が保たれ、3.でチェックして保たれたかどうか?が体感出来ると思います。
筋肉(主導筋)が縮むと逆側にある筋肉(拮抗筋)は、伸びようとする筋肉の特性がありますが、通常の生活では、主動筋と、拮抗筋が共に縮むような動作が多いことから、神経と筋の調和が乱れやすいものです。
また、ただ伸ばすだけのストレッチをすることで、伸ばされて気持ちが良いのかも知れませんが、更に動ける状態を悪くする(運動機能の低下)可能性があります。アキレス腱のストレッチを十分にしたのに、肉離れを起こした…というのを体験した、または、よく耳にしたことがあるかと思います。
動きと柔軟性を高める体操に発展させたもの、いわゆる動的な弾力性を取り戻す体操や動作は、専用マシンを使って強度をあげてあげると、弾力性を取り戻しながら、弾力性を高めることも出来ます。また、継続的に行う事で、理想の動きを学習出来ますので、本来あった神経と筋の調和が整った良い状態で過ごすことが出来るようにもなりますよ。
準備体操は、先日のブログにもあった神経と筋の調和を整える様式での体操3種です。みんな会場でしていたので、え?何あの集団って感じだったのでは、無いでしょうか…笑。
整理体操にも使える基本の体操です。疲れが心配な方、また、別にレースに出場しなくても、健康体操として取り入れられますので、以下の方法をお試くださいね。

1.前屈チェックをしてみましょう。
2.次に以下の体操をしてみましょう。
ひじ引き
https://www.youtube.com/watch?v=tEwl1GrIWnA
上体振り子
https://www.youtube.com/watch?v=knj26VxFgWQ
ひざ屈伸
https://www.youtube.com/watch?v=xRn6ZeNltZ8
3.前屈チェックをしてみましょう。
あらっ不思議!!ストレッチをしたわけじゃないのに、リセットされましたね。
コレは、通常の生活で失われていた神経と筋の調和を1.でチェックして、2.の体操ををすることで、神経と筋の調和が保たれ、3.でチェックして保たれたかどうか?が体感出来ると思います。
筋肉(主導筋)が縮むと逆側にある筋肉(拮抗筋)は、伸びようとする筋肉の特性がありますが、通常の生活では、主動筋と、拮抗筋が共に縮むような動作が多いことから、神経と筋の調和が乱れやすいものです。
また、ただ伸ばすだけのストレッチをすることで、伸ばされて気持ちが良いのかも知れませんが、更に動ける状態を悪くする(運動機能の低下)可能性があります。アキレス腱のストレッチを十分にしたのに、肉離れを起こした…というのを体験した、または、よく耳にしたことがあるかと思います。
動きと柔軟性を高める体操に発展させたもの、いわゆる動的な弾力性を取り戻す体操や動作は、専用マシンを使って強度をあげてあげると、弾力性を取り戻しながら、弾力性を高めることも出来ます。また、継続的に行う事で、理想の動きを学習出来ますので、本来あった神経と筋の調和が整った良い状態で過ごすことが出来るようにもなりますよ。
2016年07月02日
準備運動について
運動前に動ける準備をするために、ストレッチングを用いるかたは、多いかと思います。
ネコや犬は、そんなことしなくても大丈夫なのに、ヒトは、しないと怪我をしたりするのでしょうか?
以前、レース前のストレッチで足が遅くなる…でも述べたように、ストレッチ等の伸ばす動作を用いる動きは、動ける状態を悪くする(運動機能の低下)可能性があります。
硬くなっている筋肉を伸ばすことで、伸ばした筋肉は、力が入りにくくなるという特性もあるからです。また、筋肉が硬い逆側の筋力に何かアクシデントがあったりもしますので、その状態で動こうとすると、主動筋以外の筋肉にストレスを与え、かえって動きが悪くする可能性があります。

では、運動前に行う準備体操は、どのようなものが良いのでしょう?
筋肉は、バネと同じですので、収縮・弛緩・伸張を繰り返すと、弾力性を取り戻すことが出来ます。リズミカルかつ、バウンディッグを伴うような体操です。
以下の方法を試してみて下さい…
1.軽くジョギングしてみましょう。
2.次に以下の体操をしてみましょう。
ひじ引き
https://www.youtube.com/watch?v=tEwl1GrIWnA
上体振り子
https://www.youtube.com/watch?v=knj26VxFgWQ
ひざ屈伸
https://www.youtube.com/watch?v=xRn6ZeNltZ8
3.軽くジョギングしてみましょう。
最初のジョギングと体操後のジョギングを比べてみて下さい。カラダが軽くなったでしょう?
本当の準備体操とは、こんな感じのものじゃないのでしょうか?
ネコや犬は、そんなことしなくても大丈夫なのに、ヒトは、しないと怪我をしたりするのでしょうか?
以前、レース前のストレッチで足が遅くなる…でも述べたように、ストレッチ等の伸ばす動作を用いる動きは、動ける状態を悪くする(運動機能の低下)可能性があります。
硬くなっている筋肉を伸ばすことで、伸ばした筋肉は、力が入りにくくなるという特性もあるからです。また、筋肉が硬い逆側の筋力に何かアクシデントがあったりもしますので、その状態で動こうとすると、主動筋以外の筋肉にストレスを与え、かえって動きが悪くする可能性があります。

では、運動前に行う準備体操は、どのようなものが良いのでしょう?
筋肉は、バネと同じですので、収縮・弛緩・伸張を繰り返すと、弾力性を取り戻すことが出来ます。リズミカルかつ、バウンディッグを伴うような体操です。
以下の方法を試してみて下さい…
1.軽くジョギングしてみましょう。
2.次に以下の体操をしてみましょう。
ひじ引き
https://www.youtube.com/watch?v=tEwl1GrIWnA
上体振り子
https://www.youtube.com/watch?v=knj26VxFgWQ
ひざ屈伸
https://www.youtube.com/watch?v=xRn6ZeNltZ8
3.軽くジョギングしてみましょう。
最初のジョギングと体操後のジョギングを比べてみて下さい。カラダが軽くなったでしょう?
本当の準備体操とは、こんな感じのものじゃないのでしょうか?
2016年06月29日
足の役割をお手伝いする…魔法のシューズ
私達が運動指導をしている際に特に気を付けて見ている点について勉強会を行いました。
この度は、あしの健康を考える…についてです。

あしの役割は、以下の4点…
1.体重を支える
2.可動性を支える
3.地面の情報を伝える
4.血液循環を助ける
この役割を妨げるものが多かったためか、偏平足・足底筋膜炎・タコやウオノメ・外反母趾等々の足のトラブルに悩まされる方も少なくなかったかと思うのです。
ジムでも「あしの健康を考える」と称して、あしのメカニズム等についてご紹介する講座をご用意致しました。是非ご参加下さいね。
また、あしの役割をお手伝いするための専用シューズがご用意出来ました。数に限りがありますので、お早目にご予約下さい。
この度は、あしの健康を考える…についてです。

あしの役割は、以下の4点…
1.体重を支える
2.可動性を支える
3.地面の情報を伝える
4.血液循環を助ける
この役割を妨げるものが多かったためか、偏平足・足底筋膜炎・タコやウオノメ・外反母趾等々の足のトラブルに悩まされる方も少なくなかったかと思うのです。
ジムでも「あしの健康を考える」と称して、あしのメカニズム等についてご紹介する講座をご用意致しました。是非ご参加下さいね。
また、あしの役割をお手伝いするための専用シューズがご用意出来ました。数に限りがありますので、お早目にご予約下さい。
2016年06月13日
GLUT 4を刺激する運動で糖尿対策!
30分の早歩き…少し小慣れてきたら少し強度を上げてみましょう。
接地時間を短くし、重心位置をやや前に持つことで、同じキョリ・スピードであっても出力を下げられ運動量も上げられます。
通常の早歩きよりも、体幹の筋群やお尻など、カラダの中心にある筋を使って、運動することが出来ます。
早歩きの最中は、酵素のGLUT (グルット)4が刺激され、筋細胞が余分な血糖を引き取ってくれます。
余分な血糖が筋細胞に移動すると、血液中の糖分は減ります。
血液中に余分な糖分があると、それがやがては体内の脂肪になります。

よって、GLUT 4を刺激して、血糖を下げれば、太り難い代謝のいいカラダになります。
もちろん、糖尿病対策にもなります。
そのGLUT 4は、カラダの中央にある大きな筋に豊富に含まれています。
接地時間を短くし、重心位置をやや前に持つことで、同じキョリ・スピードであっても出力を下げられ運動量も上げられます。
通常の早歩きよりも、体幹の筋群やお尻など、カラダの中心にある筋を使って、運動することが出来ます。
早歩きの最中は、酵素のGLUT (グルット)4が刺激され、筋細胞が余分な血糖を引き取ってくれます。
余分な血糖が筋細胞に移動すると、血液中の糖分は減ります。
血液中に余分な糖分があると、それがやがては体内の脂肪になります。

よって、GLUT 4を刺激して、血糖を下げれば、太り難い代謝のいいカラダになります。
もちろん、糖尿病対策にもなります。
そのGLUT 4は、カラダの中央にある大きな筋に豊富に含まれています。
2016年06月09日
1年で6キロもダイエット出来る方法
ブラブラ歩くと1分間に2.7Kcal
普通に歩くと1分間に3.3Kcal
大股でサッサと歩くと1分間に4.2Kacl
大股で力強く息を切って歩くと7.9Kcal
早歩きで1分歩くと5Kacl消費します。

1Kgの脂肪を燃焼するのに約7000Kaclの消費が必要です。
30分の早歩きを毎日行うと1年で6キロもの脂肪が落ちることになりますね。
普通に歩くと1分間に3.3Kcal
大股でサッサと歩くと1分間に4.2Kacl
大股で力強く息を切って歩くと7.9Kcal
早歩きで1分歩くと5Kacl消費します。

1Kgの脂肪を燃焼するのに約7000Kaclの消費が必要です。
30分の早歩きを毎日行うと1年で6キロもの脂肪が落ちることになりますね。
2016年06月08日
股関節痛や股関節症を予防する
短距離走や跳躍は、負荷・強度の高い運動です。
最近の研究で、25~50歳の女性を対象に、最低10回以上続けてピョンピョンとその場で飛んでもらう運動を、1日2回、4カ月間続けてもらったところ、驚くほど骨密度が上がったのだそうです。
2005年の女性アスリートを対象とした研究では、バレーボール・ハードル・スカッシュ・サッカー・スピードスケードなど、カラダに負荷のかかる衝撃度の強い運動をしているヒトは、ウェイトリフティングに比べて骨密度が高いことがわかりました。

しかし、ウェイトリフティングの選手も、自転車や水泳などほとんど衝撃のないスポーツの選手よりは、健康的な骨だったそうです。
6000人以上の閉経後の女性を対象とした大規模な健康調査によると、週4回以上キビキビと歩いている人ヒト…いわゆる早歩きの傾向があるヒトは、ゆっくり歩いているヒト、そこまでの頻度で歩いていないヒト、まったく歩いていないヒトよりも、股関節骨折になる危険性がかなり低いことがわかりました。
股関節骨折は、骨の間接的かつ実用的な健康の指標にもなっています。
この時期おススメの30分の早歩きでお困りになる前の予防を始めましょう。
最近の研究で、25~50歳の女性を対象に、最低10回以上続けてピョンピョンとその場で飛んでもらう運動を、1日2回、4カ月間続けてもらったところ、驚くほど骨密度が上がったのだそうです。
2005年の女性アスリートを対象とした研究では、バレーボール・ハードル・スカッシュ・サッカー・スピードスケードなど、カラダに負荷のかかる衝撃度の強い運動をしているヒトは、ウェイトリフティングに比べて骨密度が高いことがわかりました。

しかし、ウェイトリフティングの選手も、自転車や水泳などほとんど衝撃のないスポーツの選手よりは、健康的な骨だったそうです。
6000人以上の閉経後の女性を対象とした大規模な健康調査によると、週4回以上キビキビと歩いている人ヒト…いわゆる早歩きの傾向があるヒトは、ゆっくり歩いているヒト、そこまでの頻度で歩いていないヒト、まったく歩いていないヒトよりも、股関節骨折になる危険性がかなり低いことがわかりました。
股関節骨折は、骨の間接的かつ実用的な健康の指標にもなっています。
この時期おススメの30分の早歩きでお困りになる前の予防を始めましょう。
2016年06月07日
安静時の4倍も効果あるなんて…
30分の早歩きは、4メッツの運動です。メッツとは、身体活動の強度を表す単位。
安静時の酸素摂取量3.5mL/分(体重1kgあたり)に対して、歩く・走る・自転車に乗るなどの何らかの身体活動を行ったとき、何倍の酸素を必要とするかという基準から算出されています。
安静時を1メッツ。つまり、安静時の4倍に相当します。

ダイエットのために食事を減らそうっていう方が多いと思います。実は、食事のカロリーは、差ほど減らす必要が無く、減ってしまった活動量を増やすだけで、解消出来ると思います。
早歩きは、中強度の強さの運動。または、ニコニコペースの運動ともいわれ、続けることで、糖や脂質の代謝が活発になり内臓脂肪が減少します。
早歩きは、循環器疾患・脳血管疾患の発症予防や生活習慣病予防に有効なのですね。
安静時の酸素摂取量3.5mL/分(体重1kgあたり)に対して、歩く・走る・自転車に乗るなどの何らかの身体活動を行ったとき、何倍の酸素を必要とするかという基準から算出されています。
安静時を1メッツ。つまり、安静時の4倍に相当します。

ダイエットのために食事を減らそうっていう方が多いと思います。実は、食事のカロリーは、差ほど減らす必要が無く、減ってしまった活動量を増やすだけで、解消出来ると思います。
早歩きは、中強度の強さの運動。または、ニコニコペースの運動ともいわれ、続けることで、糖や脂質の代謝が活発になり内臓脂肪が減少します。
早歩きは、循環器疾患・脳血管疾患の発症予防や生活習慣病予防に有効なのですね。
2016年06月03日
え! あしの長い・短いで加齢度合いを見分ける法?!
骨・筋・神経などの機能が衰え、転倒や骨折などにより、要介護や寝たきりになってしまう…または、そのリスクが高くなることをロコモティブ症候群と呼んでいます。
ロコモティブ症候群の原因は、加齢による運動機能の低下です。

20歳以降の下肢筋力は、年1%ずつ低下し、あしコシの衰えが顕著になる高齢になると転倒や骨折などのリスクが高まります。
年齢と歩行スピードも20歳から10年で1~2%ずつ低下する傾向があります。
みなさんも2つの歩幅を計測して、ロコモティブ症候群の度合いを自己チェックしてみてください。
2歩幅(cm)÷身長=2ステップ値
50代で1.56~1.61 60代で1.53~1.58 この辺りが年代相応の歩幅となります。
ロコモティブ症候群の原因は、加齢による運動機能の低下です。

20歳以降の下肢筋力は、年1%ずつ低下し、あしコシの衰えが顕著になる高齢になると転倒や骨折などのリスクが高まります。
年齢と歩行スピードも20歳から10年で1~2%ずつ低下する傾向があります。
みなさんも2つの歩幅を計測して、ロコモティブ症候群の度合いを自己チェックしてみてください。
2歩幅(cm)÷身長=2ステップ値
50代で1.56~1.61 60代で1.53~1.58 この辺りが年代相応の歩幅となります。
2016年05月30日
2種類の認知症予防
認知症を引き起こす原因は、脳の血管が詰まってその先に血液が行かなくなることで起こる脳血管性認知症、神経細胞の表面に蓄積するβアミロイドという異常なたんぱく質のかたまりの蓄積によるアルツハイマー型認知症の二つのパターンに別けられます。
脳血管性認知症は、先日より述べている週3日程度、30分の早歩きをすることで動脈硬化を予防することが出来て、認知症予防につながると期待されています。

アミロイドβは、インスリン分解酵素によって破壊され、脳に蓄積されないようにすることが出来ます。
この酵素が血液中に一定量あればアミロイドβがどんどん脳にたまることは、ありません。
週3日、30分の早歩きをすることで、インスリンが過剰に分泌しないように、血糖値コントロールすることが出来ます。
つまり、アミロイドβを破壊する余裕が出来て、アルツハイマー型認知症の予防につながると期待されています。
脳血管性認知症は、先日より述べている週3日程度、30分の早歩きをすることで動脈硬化を予防することが出来て、認知症予防につながると期待されています。

アミロイドβは、インスリン分解酵素によって破壊され、脳に蓄積されないようにすることが出来ます。
この酵素が血液中に一定量あればアミロイドβがどんどん脳にたまることは、ありません。
週3日、30分の早歩きをすることで、インスリンが過剰に分泌しないように、血糖値コントロールすることが出来ます。
つまり、アミロイドβを破壊する余裕が出来て、アルツハイマー型認知症の予防につながると期待されています。
2016年05月28日
投手のための物理学
打者のための物理学でちょっと触れましたが、あのピッチャーは、重い球を投げる…のお話に触れてみましょう。
投手が投げる球には、重い球と軽い球があり、重い球は、バットに当たった時に、押し込むようになるから飛ばず、軽い球は、当たった瞬間に飛んで行くので遠くまで飛ぶと言う例え方でしょうね。昔、巨人の星という漫画で、星飛雄馬の球が速いのにバッターに通用しないのは、軽い球だから…と評価するシーンがあります。これを信じてしまってる指導者が多いのですね。年代的に仕方ないかもしれない 笑。
もし、バットを押し返す球が存在するならば、球がバットに当たっていた時間が長くなりますので、それは逆に遠くに飛ばされてしまうので、カラダを上手に使える打者に当たった投手は、要注意ですね。

投手は、速い球を投げらるに越したことはありませんが、速い球でなくても、いかに長い時間バットに球を当てさせないでおくか?、打者に体幹を上手く使って球をバットに乗せさせないような間合いなどの工夫することが大事です。
ボールの企画は、規定されていますし、バットの企画も規定されていますので、精神論に邪魔されなければ、意外と目標にすぐ到達出来ると思います。しかし、選手生活は、非常に短いものですし、トレーニングでカラダを変化させるにも時間がかかりますので、トレーニングプランにもこのような含みを持たせてプログラミングしてあげると、効果も上がりやすく、非常に楽しく練習に取り組めると思うのですね。選手も頭使わないとダメだと思います。
実は、打者のための物理学をアップしたら、メールで多数のお問い合わせがあったのです。野球って、また違った面でも熱いのですね。
投手が投げる球には、重い球と軽い球があり、重い球は、バットに当たった時に、押し込むようになるから飛ばず、軽い球は、当たった瞬間に飛んで行くので遠くまで飛ぶと言う例え方でしょうね。昔、巨人の星という漫画で、星飛雄馬の球が速いのにバッターに通用しないのは、軽い球だから…と評価するシーンがあります。これを信じてしまってる指導者が多いのですね。年代的に仕方ないかもしれない 笑。
もし、バットを押し返す球が存在するならば、球がバットに当たっていた時間が長くなりますので、それは逆に遠くに飛ばされてしまうので、カラダを上手に使える打者に当たった投手は、要注意ですね。

投手は、速い球を投げらるに越したことはありませんが、速い球でなくても、いかに長い時間バットに球を当てさせないでおくか?、打者に体幹を上手く使って球をバットに乗せさせないような間合いなどの工夫することが大事です。
ボールの企画は、規定されていますし、バットの企画も規定されていますので、精神論に邪魔されなければ、意外と目標にすぐ到達出来ると思います。しかし、選手生活は、非常に短いものですし、トレーニングでカラダを変化させるにも時間がかかりますので、トレーニングプランにもこのような含みを持たせてプログラミングしてあげると、効果も上がりやすく、非常に楽しく練習に取り組めると思うのですね。選手も頭使わないとダメだと思います。
実は、打者のための物理学をアップしたら、メールで多数のお問い合わせがあったのです。野球って、また違った面でも熱いのですね。
2016年05月27日
運動強度が物足りないと言われる方へ
運動強度が強くなると、糖質からのエネルギーに依存することが知られています。
ですので、運動強度が物足りないと言って簡単に強度の強い運動をすると脂肪よりも糖のエネルギーを利用することになります。

ヒトのカラダには、糖を利用する解糖系エンジン、脂肪を利用するミトコンドリアエンジンの2つのエンジンがあります。若い頃は、解糖系エンジンをしっかり使って運動していましたが、40歳を過ぎた頃から、解糖系エンジンは、お休みしがちになり、ミトコンドリアエンジンをよく使うようになります。
ですので、運動強度が物足りないからと言って働いてない解糖系エンジンを使おうとすると負のものがカラダに残るようになります。
また、カラダに蓄えられる糖質は、1%程度しかないので、常に食事からの摂取が必要となるのも事実ですが、食事による1日の摂取エネルギーが2500kcal程度の場合、食パン1枚と普通茶碗3.5杯くらい。
運動強度が物足りない…、やった感がしない…
なかなか痩せないのは、運動強度のせいじゃないっていうのをご理解いただけたでしょうか?
ですので、運動強度が物足りないと言って簡単に強度の強い運動をすると脂肪よりも糖のエネルギーを利用することになります。

ヒトのカラダには、糖を利用する解糖系エンジン、脂肪を利用するミトコンドリアエンジンの2つのエンジンがあります。若い頃は、解糖系エンジンをしっかり使って運動していましたが、40歳を過ぎた頃から、解糖系エンジンは、お休みしがちになり、ミトコンドリアエンジンをよく使うようになります。
ですので、運動強度が物足りないからと言って働いてない解糖系エンジンを使おうとすると負のものがカラダに残るようになります。
また、カラダに蓄えられる糖質は、1%程度しかないので、常に食事からの摂取が必要となるのも事実ですが、食事による1日の摂取エネルギーが2500kcal程度の場合、食パン1枚と普通茶碗3.5杯くらい。
運動強度が物足りない…、やった感がしない…
なかなか痩せないのは、運動強度のせいじゃないっていうのをご理解いただけたでしょうか?
2016年05月24日
このシーズンおススメ 30分の早歩きのデメリット
早歩きは、普通の歩き方よりスピードを上げるために脚の動きが速くなります。
そのため、動作のすべてがせわしなく見えるかも知れません。
例えば…着地では、足をフラットに着地させて衝撃を和らげるようにしています。
着地と言うより、足の裏全体で地面を抑えるようにすることで、足や膝などにかかる負担をさらに軽くすることが出来ます。

平地を歩いている時でも、膝には瞬間的に体重の3倍程度の重さがかかります。
例えば…体重70キログラムのヒト…210キログラムもの重さが片方の膝にかかるのですから、侮れません。
股関節・腰・首なども同様に大きな衝撃が加わっています。
速く歩くためには、脚だけではなく、骨盤の切り替えし動作も伴います。
このように…1つ1つの動作が雑になることが予測されることから、簡単に身に着けるためのドリル練習&やまおく体操をご紹介しています。
そのため、動作のすべてがせわしなく見えるかも知れません。
例えば…着地では、足をフラットに着地させて衝撃を和らげるようにしています。
着地と言うより、足の裏全体で地面を抑えるようにすることで、足や膝などにかかる負担をさらに軽くすることが出来ます。

平地を歩いている時でも、膝には瞬間的に体重の3倍程度の重さがかかります。
例えば…体重70キログラムのヒト…210キログラムもの重さが片方の膝にかかるのですから、侮れません。
股関節・腰・首なども同様に大きな衝撃が加わっています。
速く歩くためには、脚だけではなく、骨盤の切り替えし動作も伴います。
このように…1つ1つの動作が雑になることが予測されることから、簡単に身に着けるためのドリル練習&やまおく体操をご紹介しています。
2016年05月23日
このシーズンおススメ 30分の早歩きのメリット
早歩きは、ランニングほど運動強度が強くないため、誰にでも手軽にスタートできます。
筋には、スピードを出すことが得意な速筋と、持久力に優れた遅筋があります。短距離走では速筋が主に使われ、早歩きでは、速筋と遅筋の両方を使います。速筋は、体内の糖質を主なエネルギー源としていますが、遅筋は糖質も脂肪も両方を使えます。
そのため、早歩きでは、余分に摂った糖質も消費し、さらにすでに体内にたまっている脂肪も燃やしてエネルギー源にしてくれます。

早歩きは、普通に歩くよりは、消費力ロリーが大きく、スリムになる効果が高くなります。また、ランニングに比べて、心臓への負担が減らすことが出来、腰・膝にかかる衝撃や重さの負担も少なくなります。
早歩きを継続することで、適度な脚力も養われます。
体内に吸収された必要以上の糖質は、やがて脂肪として蓄えられますが、同じカロリーの食事をしていても、早歩きで消費するカロリーを増やすことで、体内に残った脂肪に変わる糖質をも減らすことが出来るでしょう。
筋には、スピードを出すことが得意な速筋と、持久力に優れた遅筋があります。短距離走では速筋が主に使われ、早歩きでは、速筋と遅筋の両方を使います。速筋は、体内の糖質を主なエネルギー源としていますが、遅筋は糖質も脂肪も両方を使えます。
そのため、早歩きでは、余分に摂った糖質も消費し、さらにすでに体内にたまっている脂肪も燃やしてエネルギー源にしてくれます。

早歩きは、普通に歩くよりは、消費力ロリーが大きく、スリムになる効果が高くなります。また、ランニングに比べて、心臓への負担が減らすことが出来、腰・膝にかかる衝撃や重さの負担も少なくなります。
早歩きを継続することで、適度な脚力も養われます。
体内に吸収された必要以上の糖質は、やがて脂肪として蓄えられますが、同じカロリーの食事をしていても、早歩きで消費するカロリーを増やすことで、体内に残った脂肪に変わる糖質をも減らすことが出来るでしょう。
2016年05月20日
打者のための物理学
トレーニング指導をしてる際に、同業者の中に理系の方が少ないのか?、つじつまが合わなくなると、気合を入れろ!などの精神論に逃げるヒトも少なくありません 笑。例えば、あのピッチャーは、重たい球を投げるとか、よく耳にしますが、ボールの企画は、規定されていますし、バットの企画も規定されていますので、精神論に邪魔されなければ、全て数字で計算出来るのです。
では、打つことについて考えてみましょう…

速い打球は、バットで遠くまで飛ばすことが出来ます。速い打球を打つためには、どうすれば良いでしょう?パワー増強・良いバットを選ぶ・球を真芯で捉える…等のキーワードが頭に浮かびますね。運動は、運動量と力積(mV-mv=Ft)で表わすことが出来ます。
m:野球の球の質量
V:打つ直前の投球の速度
v:打った直後の打球の速度
F:球に加わった力
t:球がバットに当たっていた時間
投球と打球は、反対方向に進みますので、もし目の前の投手が球速150kmで投げたとして、打者が150kmで打球を打ったならならば、vは、-150kmということになります。もし、打球が速ければ、等号の左側の値が大きくなります。つまり、速い打球を打つためには、等号の右側の部分の球に加わった力×球がバットに当たっていた時間を大きくすれば良いと言うことです。
その力を大きくするために、よく間違えるのが、筋量を増やす努力をさせてしまうこと。筋量が増えたから、力が大きくなると考えてしまうのでしょうね…巨人の星の大リーグボール養成ギブスの性かな…お気持ちは、わかるんだけれど、迷惑なシーンです 笑。ここでの力は、パワー。力×速度ですので、mgvになります。ですので、普段の練習において、筋力をつける練習が誤っていることに気づいて欲しいです。
また、球がバットに当たっていた時間を長くすることによって、速い打球を遠くへ飛ばせるようになります。例えば、バットに当たっている時間が0.1秒であったのを0.2秒に出来れば、打球の速度を倍に出来ます。
打撃の際に腰を使って打て!とのニュアンスでの指導は、このことなのですね。腕振りだけでバットを球にタッチすると、球がバットに当たっていた時間が短くなり、打球の速度が上がりません。腰を使って(に見える…)の動作を加えることで、バットに球を乗せて運ぶような状態に近づきますので、球がバットに当たっていた時間が長くなり、打球の速度が上がり、より遠くに球を飛ばせるようになります。
では、打つことについて考えてみましょう…

速い打球は、バットで遠くまで飛ばすことが出来ます。速い打球を打つためには、どうすれば良いでしょう?パワー増強・良いバットを選ぶ・球を真芯で捉える…等のキーワードが頭に浮かびますね。運動は、運動量と力積(mV-mv=Ft)で表わすことが出来ます。
m:野球の球の質量
V:打つ直前の投球の速度
v:打った直後の打球の速度
F:球に加わった力
t:球がバットに当たっていた時間
投球と打球は、反対方向に進みますので、もし目の前の投手が球速150kmで投げたとして、打者が150kmで打球を打ったならならば、vは、-150kmということになります。もし、打球が速ければ、等号の左側の値が大きくなります。つまり、速い打球を打つためには、等号の右側の部分の球に加わった力×球がバットに当たっていた時間を大きくすれば良いと言うことです。
その力を大きくするために、よく間違えるのが、筋量を増やす努力をさせてしまうこと。筋量が増えたから、力が大きくなると考えてしまうのでしょうね…巨人の星の大リーグボール養成ギブスの性かな…お気持ちは、わかるんだけれど、迷惑なシーンです 笑。ここでの力は、パワー。力×速度ですので、mgvになります。ですので、普段の練習において、筋力をつける練習が誤っていることに気づいて欲しいです。
また、球がバットに当たっていた時間を長くすることによって、速い打球を遠くへ飛ばせるようになります。例えば、バットに当たっている時間が0.1秒であったのを0.2秒に出来れば、打球の速度を倍に出来ます。
打撃の際に腰を使って打て!とのニュアンスでの指導は、このことなのですね。腕振りだけでバットを球にタッチすると、球がバットに当たっていた時間が短くなり、打球の速度が上がりません。腰を使って(に見える…)の動作を加えることで、バットに球を乗せて運ぶような状態に近づきますので、球がバットに当たっていた時間が長くなり、打球の速度が上がり、より遠くに球を飛ばせるようになります。
2016年05月16日
歩くのが速い国ランキング
東京に行くと、みんな歩くのがとても速いぃという印象があります。讃岐人は、車社会。せっかちな運転が目に余りますが、案外のんびりしているのかなぁとも思います。
そんなところも糖尿病受診率の高さに関係あったりして…
ちょっと調べてみると、日本は、世界ランク20位程度。そんなに速く歩く理由は、よく分かりませんが、イギリスの国際文化交流機関の調査による歩行速度都市別ランキングによると…

1.シンガポール 10秒55
2.デンマーク (コペンハーゲン) 10秒82
3.スペイン (マドリード) 10秒89
4.中国 (広東省広州市) 10秒94
5.アイルランド (ダブリン) 11秒03
6.ブラジル (クリチバ) 11秒13
7.ドイツ (ベルリン) 11秒16
8.アメリカ (ニューヨーク) 12秒00
9.オランダ (ユトレヒト) 12秒04
10.オーストリア (ウィーン) 12秒06
・・・
19.日本 (東京) 12秒83
ちなみに歩行速度が最も遅かったのは、マラウイのブランタイアとバーレーンのマナマだったそうです。
身長差や歩幅は、差ほど関係ないようで、知らぬ間に行き急いで生活しているのが現代人。
イギリス心理学者リチャード・ワイズマン教授によると、たまには立ち止まって考えて、ゆっくり歩むのも悪くないとコメントされていましたね。
そんなところも糖尿病受診率の高さに関係あったりして…
ちょっと調べてみると、日本は、世界ランク20位程度。そんなに速く歩く理由は、よく分かりませんが、イギリスの国際文化交流機関の調査による歩行速度都市別ランキングによると…

1.シンガポール 10秒55
2.デンマーク (コペンハーゲン) 10秒82
3.スペイン (マドリード) 10秒89
4.中国 (広東省広州市) 10秒94
5.アイルランド (ダブリン) 11秒03
6.ブラジル (クリチバ) 11秒13
7.ドイツ (ベルリン) 11秒16
8.アメリカ (ニューヨーク) 12秒00
9.オランダ (ユトレヒト) 12秒04
10.オーストリア (ウィーン) 12秒06
・・・
19.日本 (東京) 12秒83
ちなみに歩行速度が最も遅かったのは、マラウイのブランタイアとバーレーンのマナマだったそうです。
身長差や歩幅は、差ほど関係ないようで、知らぬ間に行き急いで生活しているのが現代人。
イギリス心理学者リチャード・ワイズマン教授によると、たまには立ち止まって考えて、ゆっくり歩むのも悪くないとコメントされていましたね。
2016年05月15日
30分の早歩き 消費エネルギーは、セックスと同じ?!
消費カロリーは、基礎代謝+活動による代謝によって構成されています。
基礎代謝は、性別・年齢により個人差がありますが、黙っていても消費するカロリー。継続的にカラダに負荷を与え続けるトレーニングによって、筋肉量(筋細胞)を増やす事で、ある程度高める事が出来ます。
活動による代謝は、動くことによって消費するカロリー。通勤や通学、仕事や家事、運動する等によってその日のカロリー消費を高めることが出来ます。
生活や運動の強度は、メッツ(METs:メッツ)を使って表すと分かりやすいと思います。睡眠時(安静時)の運動強度を1METsとしたとき、消費するカロリーが2倍なら2METs。3倍なら3METsと表記します。

METsを使用するのは、体重によって消費カロリーが違うからです。ちなみに、METsから消費カロリーを算出するには、以下の公式で表します。
・消費カロリー=METs×時間(h)×体重(kg)
例えば、体重66キロの人が2METsの運動(活動)を1時間行う事で消費されるカロリーは、2×1×66=132(キロカロリー)という事になります。
僕が推奨する早歩きは、4メッツ。実は、セックスと同じ消費カロリーと言われています。
年齢を追うごとに、夫婦間での早歩きの重要性は、こんなところからも気になるところです 笑。
基礎代謝は、性別・年齢により個人差がありますが、黙っていても消費するカロリー。継続的にカラダに負荷を与え続けるトレーニングによって、筋肉量(筋細胞)を増やす事で、ある程度高める事が出来ます。
活動による代謝は、動くことによって消費するカロリー。通勤や通学、仕事や家事、運動する等によってその日のカロリー消費を高めることが出来ます。
生活や運動の強度は、メッツ(METs:メッツ)を使って表すと分かりやすいと思います。睡眠時(安静時)の運動強度を1METsとしたとき、消費するカロリーが2倍なら2METs。3倍なら3METsと表記します。

METsを使用するのは、体重によって消費カロリーが違うからです。ちなみに、METsから消費カロリーを算出するには、以下の公式で表します。
・消費カロリー=METs×時間(h)×体重(kg)
例えば、体重66キロの人が2METsの運動(活動)を1時間行う事で消費されるカロリーは、2×1×66=132(キロカロリー)という事になります。
僕が推奨する早歩きは、4メッツ。実は、セックスと同じ消費カロリーと言われています。
年齢を追うごとに、夫婦間での早歩きの重要性は、こんなところからも気になるところです 笑。
2016年05月14日
レース前のストレッチで足が遅くなる…
可動域を広げるのが目的で行うストレッチ…実は、競技前のストレッチがパフォーマンスを低下させると先日のTVでも放送されていました。
3~10分の静的ストレッチングの前後で筋力を測定すると、最大挙上負荷、等速性筋力などの動的筋力(McLellan ら、2000;Cramer ら、2004など)、等尺性筋力および筋力発揮速度(Nelson ら、2000など)がいずれも低下してしまうことが示されています。
筋力低下は、最大で約30%にも及び、その効果はストレッチング終了後45分間ほど持続するそうです。
また、筋力低下と平行して、筋の電気的活動も低下することから(Fowles ら、2000)、この筋力低下は、筋線維の動員能力の低下によることが示唆されます。
ここでの筋力低下のメカニズム…
筋には、筋紡錘という受容器があり、筋の長さを検知していますが、筋紡錘が伸張されると、感覚信号が脊髄や脳の中枢神経系に送られます。このとき、脊髄中にある運動神経(α-運動神経)の活動を増強し、伸張された筋の活動を高めるように作用します。これを伸張反射といいます。
筋が伸張されると、これに抗して大きな筋力を意識しなくとも瞬時に発揮できるような仕組みとなっています(やまおく体操は、ここを自分のカラダを重りとして活用することで、神経と筋の調和が整うよう応用された体操です)。
一方、筋紡錘の内部にも、錘内線維と呼ばれる筋線維があり、運動神経による支配を受けています(γ-運動神経)。錘内線維は、筋紡錘の感度を調節していて、γ-運動神経が活動すると筋紡錘の感度が上がります。
最大筋力を発揮するときには、αとγの両方の運動神経が活動し、筋紡錘からの感覚信号によってさらに筋力発揮が増強される仕組みがはたらきます。これをγ-α共役と呼びます。

静的ストレッチングにより、筋紡錘の感度が低下し(脱感作)、その結果、筋の緊張は低減するものの、γ-α共役がうまくはたらかなくなって筋力も低下する可能性があるのです。
僕は、競技前にストレッチングすると、カラダが逆に重く感じたりするので、あまり真面目に取り組んでいませんでした。
カラダが柔らかいのに越したことはありませんが、可動域を広げても、骨や関節を動かすための筋がうまく作用しなければ、競技成績に逆に悪い影響を与えてしまうという持論がありましたので、先生やコーチに嫌がられましたが、持論を通していたのを思い出します。
競技前のストレッチがパフォーマンスを低下させる…特に筋力・パワー系競技のアスリートにとって要注意でもありますね。
3~10分の静的ストレッチングの前後で筋力を測定すると、最大挙上負荷、等速性筋力などの動的筋力(McLellan ら、2000;Cramer ら、2004など)、等尺性筋力および筋力発揮速度(Nelson ら、2000など)がいずれも低下してしまうことが示されています。
筋力低下は、最大で約30%にも及び、その効果はストレッチング終了後45分間ほど持続するそうです。
また、筋力低下と平行して、筋の電気的活動も低下することから(Fowles ら、2000)、この筋力低下は、筋線維の動員能力の低下によることが示唆されます。
ここでの筋力低下のメカニズム…
筋には、筋紡錘という受容器があり、筋の長さを検知していますが、筋紡錘が伸張されると、感覚信号が脊髄や脳の中枢神経系に送られます。このとき、脊髄中にある運動神経(α-運動神経)の活動を増強し、伸張された筋の活動を高めるように作用します。これを伸張反射といいます。
筋が伸張されると、これに抗して大きな筋力を意識しなくとも瞬時に発揮できるような仕組みとなっています(やまおく体操は、ここを自分のカラダを重りとして活用することで、神経と筋の調和が整うよう応用された体操です)。
一方、筋紡錘の内部にも、錘内線維と呼ばれる筋線維があり、運動神経による支配を受けています(γ-運動神経)。錘内線維は、筋紡錘の感度を調節していて、γ-運動神経が活動すると筋紡錘の感度が上がります。
最大筋力を発揮するときには、αとγの両方の運動神経が活動し、筋紡錘からの感覚信号によってさらに筋力発揮が増強される仕組みがはたらきます。これをγ-α共役と呼びます。

静的ストレッチングにより、筋紡錘の感度が低下し(脱感作)、その結果、筋の緊張は低減するものの、γ-α共役がうまくはたらかなくなって筋力も低下する可能性があるのです。
僕は、競技前にストレッチングすると、カラダが逆に重く感じたりするので、あまり真面目に取り組んでいませんでした。
カラダが柔らかいのに越したことはありませんが、可動域を広げても、骨や関節を動かすための筋がうまく作用しなければ、競技成績に逆に悪い影響を与えてしまうという持論がありましたので、先生やコーチに嫌がられましたが、持論を通していたのを思い出します。
競技前のストレッチがパフォーマンスを低下させる…特に筋力・パワー系競技のアスリートにとって要注意でもありますね。
2016年05月13日
自律神経をコントロールさせる方法をご紹介!
本来このシーズンは、自律神経の副交感神経が優位に働いてリラックスモードになるはずなのですが、今季は、さほど寒くも無かったのに、暖房器具を使って快適に過ごしたり、冷え性を心配して靴下をはいて寝たり、電気毛布にくるまって休むなどのカラダに対してついつい甘やかせた生活を送られてきた方々は、実感は、少ないかも知れませんが、副交感神経が優位に働き辛くなっているはずです。
自律神経の副交感神経が優位に働いてリラックスモードになるはずが、交感神経ばかりがはたらいてしまうために、疲労や不調をかかえてしまいがちです(痛いところがあって病院に行ったら年寄り病とか言われてしまった…等)。
本来の健康的なカラダを取りもどすためには、自律神経を整えること、つまり副交感神経を優位にすることがとても大切。しかし、自律神経は、自分でコントロールすることが出来ませんので、交感神経を刺激せずに副交感神経の働きをグッと下げる効果が期待出来る当社開発のリセットバイクでの運動を通常のプランの間に採用しながら、本来のこの時期の働きを取り戻しましょう。

また、鍛える時期にきちんと鍛えられなかった方は、このステージでのトレーニングをしっかりすることで、持久力をつけるためのベースも作りやすくなりますので、今度こそ、しっかり頑張ってみましょう。
理想では、1日置きか、2日置きでのエクササイズを月に8~10回程度するのが目標です。
物が豊富になり、年中いつでも品物が手に入るようになったのと、便利になったのもあって、現代人は、エネルギーを摂り過ぎている傾向にあるかも知れません。余剰なエネルギーは、上へ上へと登る性質があり、頭に溜まりやすくなります。エネルギーは、摂らないといけないのですが、要らないものをしっかり排出してからエネルギー摂取しないと、余りのエネルギーで負のものを生み出してしまうことになるかも知れません。いくら医療が発達しても、悪性新生物・脳卒中・血管系の病は、減ることが無いのは、その理由の1つになっているかも知れません。
この時期、いまひとつ体調が優れない方は、ちょっと前の日本の暮らし方を真似てみると良いかも知れませんね。カラダってこんなにも温かかったのかな…等、いろんな気付きに出会えるかも知れませんね。
当センターでは…
A.入会したてでまだ強化出来なかった方
B.鍛える時期にお疲れが出て出来なかった方
C.しっかり鍛えられた方や元々健康な方
の3タイプの自律神経コントロールコースをご用意致しました。
・睡眠指導(すこしづつ早寝早起きに変えていく工夫)
・お風呂指導(就寝1時間前に38~40度の少しぬるめのお湯)
・食事のとり方(1食4時間以上あけておやつを含む1日4回)
・食べ物(煮魚・野菜の煮物・大豆等、外食の場合は、定食にしたり、白米ではなく雑穀米や玄米や胚芽米を選ぶ)
・お酒(飲みすぎてしまうと交感神経に切りかわってしまう)
・たばことの付き合い方(自律神経が興奮しやすく、身体的な依存だけでなく精神的にも依存する可能性)
・ストレスを受けない、ためない
・香り(香りは、感情をつかさどる脳に直結。柑橘類)
等の生活も一緒にご案内させて頂きますので、ぜひお試しください。
既にオプション講座を開講していますが、一緒に学びながら、自立を鍛えて行きましょう。
自律神経の副交感神経が優位に働いてリラックスモードになるはずが、交感神経ばかりがはたらいてしまうために、疲労や不調をかかえてしまいがちです(痛いところがあって病院に行ったら年寄り病とか言われてしまった…等)。
本来の健康的なカラダを取りもどすためには、自律神経を整えること、つまり副交感神経を優位にすることがとても大切。しかし、自律神経は、自分でコントロールすることが出来ませんので、交感神経を刺激せずに副交感神経の働きをグッと下げる効果が期待出来る当社開発のリセットバイクでの運動を通常のプランの間に採用しながら、本来のこの時期の働きを取り戻しましょう。

また、鍛える時期にきちんと鍛えられなかった方は、このステージでのトレーニングをしっかりすることで、持久力をつけるためのベースも作りやすくなりますので、今度こそ、しっかり頑張ってみましょう。
理想では、1日置きか、2日置きでのエクササイズを月に8~10回程度するのが目標です。
物が豊富になり、年中いつでも品物が手に入るようになったのと、便利になったのもあって、現代人は、エネルギーを摂り過ぎている傾向にあるかも知れません。余剰なエネルギーは、上へ上へと登る性質があり、頭に溜まりやすくなります。エネルギーは、摂らないといけないのですが、要らないものをしっかり排出してからエネルギー摂取しないと、余りのエネルギーで負のものを生み出してしまうことになるかも知れません。いくら医療が発達しても、悪性新生物・脳卒中・血管系の病は、減ることが無いのは、その理由の1つになっているかも知れません。
この時期、いまひとつ体調が優れない方は、ちょっと前の日本の暮らし方を真似てみると良いかも知れませんね。カラダってこんなにも温かかったのかな…等、いろんな気付きに出会えるかも知れませんね。
当センターでは…
A.入会したてでまだ強化出来なかった方
B.鍛える時期にお疲れが出て出来なかった方
C.しっかり鍛えられた方や元々健康な方
の3タイプの自律神経コントロールコースをご用意致しました。
・睡眠指導(すこしづつ早寝早起きに変えていく工夫)
・お風呂指導(就寝1時間前に38~40度の少しぬるめのお湯)
・食事のとり方(1食4時間以上あけておやつを含む1日4回)
・食べ物(煮魚・野菜の煮物・大豆等、外食の場合は、定食にしたり、白米ではなく雑穀米や玄米や胚芽米を選ぶ)
・お酒(飲みすぎてしまうと交感神経に切りかわってしまう)
・たばことの付き合い方(自律神経が興奮しやすく、身体的な依存だけでなく精神的にも依存する可能性)
・ストレスを受けない、ためない
・香り(香りは、感情をつかさどる脳に直結。柑橘類)
等の生活も一緒にご案内させて頂きますので、ぜひお試しください。
既にオプション講座を開講していますが、一緒に学びながら、自立を鍛えて行きましょう。